文学にゆかりある八代で「小説」と向き合う日々
八代市の文学愛好者を中心に結成された文芸サークル「木綿葉の会」に在籍し8年になる柳宗一郎さん。親ガチャ、ヤングケアラーなど現代社会に浮かび上がる様々な課題を盛り込んだ『夢のあとさき』で第45回(2023年)熊本県民文芸賞小説部門1席に選ばれるほか、小説『あわい』で第55回(2024年)九州芸術祭文学賞の熊本県地区優秀作にも輝きました。
「小さい頃から本が好きで、将来の夢として漠然と小説家になりたいと思った時期もありましたが、大学で文学を学んでいた時も、もちろん教職に就いてからも小説を書いたことはありませんでした」と語ります。
柳さんが読み手ではなく書き手として小説に時間を費やすようになったのは定年間近、59歳のときでした。「退職後に打ち込める何かを探していたときに、妻から薦められたのが木綿葉の会でした」。もともと、八代は文学にゆかりのある地。古くは不知火海に浮かぶ水島の長田王の歌碑、江戸後期に松尾芭蕉の終焉時までを記した『花屋日記』の作者として知られる正教寺(本町)住職·藁井文暁、明治期の女性運動で活躍した詩人高群逸枝などが過ごした地でもあるそう。
文学にゆかりのあるこの地で、幼い頃夢見たペンを振るう日々が待っていようとは、柳さん自身予想もしないことでした。
20周年記念し「木綿葉文芸賞」創設
自分の世界を自由に表現
ジャンルを問わず、その時々に浮かんだものをテーマにするという柳さん。「私たちのように趣味で書いている小説は、登場人物と自分を重ねられることもあるため、あえて性別や年齢など、まったく違う設定しています」と笑います。
今後柳さんの小説のベースとなるかもしれないのが学生時代に学んだ平安文学のエッセンスを取り入れたもの。「その時代の人物を自分の世界観で自由自在にあやつれるー。いろんな世界を自由に作っていけるのが小説の面白いところです」。
柳さんの所属する「木綿葉の会」では、今年設立20周年記念事業として「木綿葉文芸賞」が創設され、一般から小説とエッセーを募集するそう。「年齢や経験などは全く関係ありません。ぜひ多くの人にチャレンジしてもらいたいです」。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●柳 宗一郎さん(67歳)
1958年、上天草市生まれ。幼少期を堺市で過ごし、中学2年から八代に。八代高校から北九州の大学に進学。卒業後は八代白百合学園で教鞭をとり、学校長も務める。退職後の2017年、文芸同人「木綿葉(ゆうは)の会」に入会。熊本県民文芸賞、九州芸術祭文学賞など受賞歴多数。

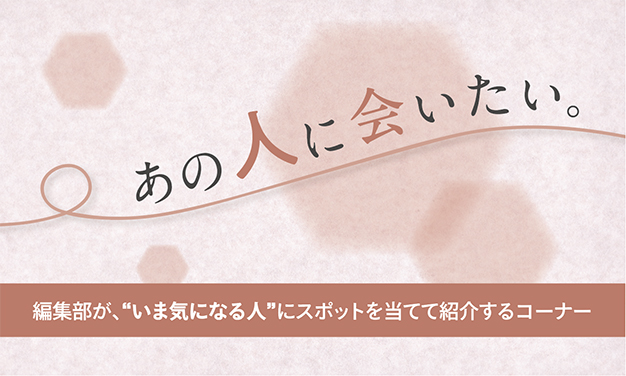


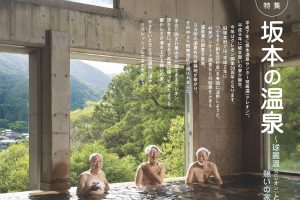
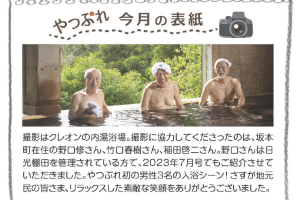
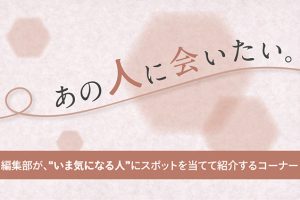




最近のコメント