2025年8月号主夫ぽんた「“市民格”という言葉」
8月に八代に帰ったときに厚生会館に関する本をいただいたんですね。その本を読んでたら初代八代市長の坂田道男さんが1962年に行われた厚生会館の落成式の式辞の中で「市民格」という言葉を使ってたんです。正確には「私のいう市民格の向上に役立ち」という感じで。私ですね、この「市民格」って言葉、すごく良いなと思ったんです。坂田さんがどういう思いでその言葉を使ったかはわからないんですが、おそらく「品格」とか「市民としての意識」みたいな意味での「市民格」なんだと思います。で、その「市民格」こそいま八代の人たちに必要なんじゃないかと。
ちなみに「市民格」って言葉をググっていただけたらわかるんですが、この言葉ってほとんど使われてないんですよね。90年代後半ぐらいから関西のほうで「都市格」って言葉は使われ始めてたらしいんですが、「市民格」って言葉は私が調べた限りでは出てきませんでした。あと「都市格」っていうのはあくまでも場所であって、人としての「市民格」とは違いますよね。八代にとってはそこもポイントだと思うんです。
今回市長に当選された小野泰輔さんが選挙中と当選後によく言ってたのが「八代を誇りに思えるまちに」という言葉です。では誇りに思えるために何をするのか。そのときにザックリ言うと「都市格」に行くのか、あるいは「市民格」に行くのかの分れ道がある、というのが私の見立てなんです。私は断然後者なんですよねー。まあどっちも大事なんですけど、八代の場合は軸足は「市民格」でしょ、と。「都市格」に走り過ぎちゃうとまたワケ分かんないもの建てたりするじゃないですか。あと「市民格」って言葉は、せっかく坂田道男初代八代市長が遺してくれた八代市民への置き土産なわけでしょ。いやホントに大事にしたほうがいいですって。
私の希望とすれば「市民格」という言葉を定義する際に今回の八代市長選で市民たちがやったこと、つまり「自分の手で社会を変える」、そういう「自分の足で立つ市民」みたいなものもぜひ含めてほしいです。アメリカからのお願いでしたー。
八代市出身。八代小→一中→南校(現:清流高校)→沖縄の大学へ
(小中高時代のあだ名は“ポンタ”)。
沖縄で海の仕事に従事→アジア放浪→渡米。
メディアで働いたあと主夫に。
アメリカ人のかみさんと息子2人の4人家族。
米国・ニュージャージー州在住。



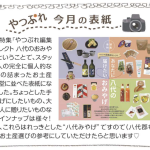



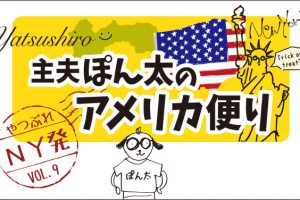

最近のコメント